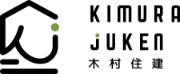2025/03/13
2025年4月、建築基準法改正により、木造2階建て住宅の構造計算書提出が義務化されます。
この改正は、住宅の安全性向上を目的としていますが、多くの住宅建築・改築を検討されている方にとって、戸惑いや不安を感じている方も少なくないでしょう。
この変化への対応をスムーズに行うために、改正の概要、影響、そして具体的な対応策を解説します。
目次
2025年4月からの建築基準法改正と木造2階建て住宅への影響
4号特例の廃止と構造計算書提出義務化の概要
2025年4月からの建築基準法改正では、これまで構造計算書の提出が免除されていた4号建築物(主に木造2階建て住宅など)に対する特例が廃止されます。
これにより、木造2階建て住宅を建築・改築する際には、構造計算書を提出することが義務化されます。
これは、住宅の安全性確保を目的とした改正であり、これまで簡略化されていた手続きが、より厳格なものへと変更されることを意味します。
改正によるメリットデメリット
改正によるメリットは、住宅の安全性向上に大きく寄与することです。
構造計算を行うことで、地震や台風などの自然災害に対する耐震性・耐風性が向上し、居住者の安全をより高めることができます。
一方、デメリットとしては、建築費用や手続きにかかる時間が増加することが挙げられます。
構造計算には専門家の費用が必要となり、建築期間も延びる可能性があります。
2025年2階建て構造計算書提出義務化への対応スケジュール
改正への対応は早めに行うことが重要です。
まず、建築計画段階で、設計者と十分な協議を行い、構造計算の内容や費用、スケジュールについて確認しましょう。
設計図書の完成後、構造計算を実施し、必要な書類を準備する必要があります。
提出期限までに余裕をもって手続きを進める計画を立てましょう。
構造計算書提出義務化に伴う費用負担
構造計算には専門家の費用が必要となります。
費用は、建物の規模や構造、設計者の選定などによって変動しますが、事前に概算費用を確認し、予算に含めることが重要です。

2025年2階建て構造計算書提出義務化への適切な対応策
構造計算の種類と選択方法
構造計算にはいくつかの種類があり、建物の規模や構造に合わせて適切な方法を選択する必要があります。
設計者と相談し、最適な方法を選択することが重要です。
建築計画における注意点
建築計画段階では、構造計算への対応を考慮した上で、建物の規模や構造、使用する材料などを決定する必要があります。
設計者と綿密な打ち合わせを行い、必要な情報を提供し、疑問点があれば積極的に質問することが大切です。
改正後の手続きの流れと必要な書類
改正後の手続きの流れは、従来とは異なる部分があります。
必要な書類や提出期限などを事前に確認し、漏れなく準備することが重要です。
設計者や建築確認申請を行う機関に確認を取りながら進めましょう。

まとめ
2025年4月からの建築基準法改正により、木造2階建て住宅の構造計算書提出が義務化されます。
この改正は、住宅の安全性向上に繋がる一方で、費用や手続きの負担増加も伴います。
しかし、早めの準備によって、スムーズな対応が可能となります。
今回は解説した内容を参考に、改正への対応を進めていきましょう。
改正後の手続きや費用負担については、専門家への相談も有効です。
安全で安心できる住宅を手に入れるために、必要な準備を怠らずに、計画的に進めてください。
当社では、2025年に義務化される2階建て構造計算書の提出にも迅速に対応できる体制を整えています。
寄棟や軒のある家づくりを推奨し、日本建築の伝統美を守りながら、屋根の耐久性や壁の長寿命化にも貢献します。